
特許申請について教えてほしい。
書類って何が必要なの?
申請から登録までどうしたらいいの?
特許の取り方も知りたい。

特許申請には、様々な書類と手続きが必要です。
初めての方にとっては、それらの内容や意味が分からず、戸惑うこともあるでしょう。
そこで本記事では、特許申請に必要な書類と取り方について解説します。

- 関西の特許事務所と大手法律事務所と大手企業知財部で合計10年ほどの知財実務を積んできました。
- 特許サポート件数1,000件以上、商標申請代行件数2,000件以上の弁理士です。
- 京都で特許事務所BrandAgentを開業しています。
- ブログ歴3年以上でブログを書くことが趣味です。
- 月間PV数最高11万超のブログを運営したこともあります。
- 初心者の方でもわかりやすいように記事を書くことが得意です。
本記事の構成
- 特許申請に必要な書類の種類と役割
- 特許申請書の作成方法とポイント
- 特許申請の手続きの流れ
- 特許申請から登録までの費用はどれくらい?
- 特許審査の流れと期間
- 特許登録後の手続きと期間
- 特許申請に関する注意点とポイント
- 特許の取り方のコツ
- 特許申請を個人でやるか弁理士に代行するか
- 特許申請のまとめ
特許申請に必要な書類の種類と役割
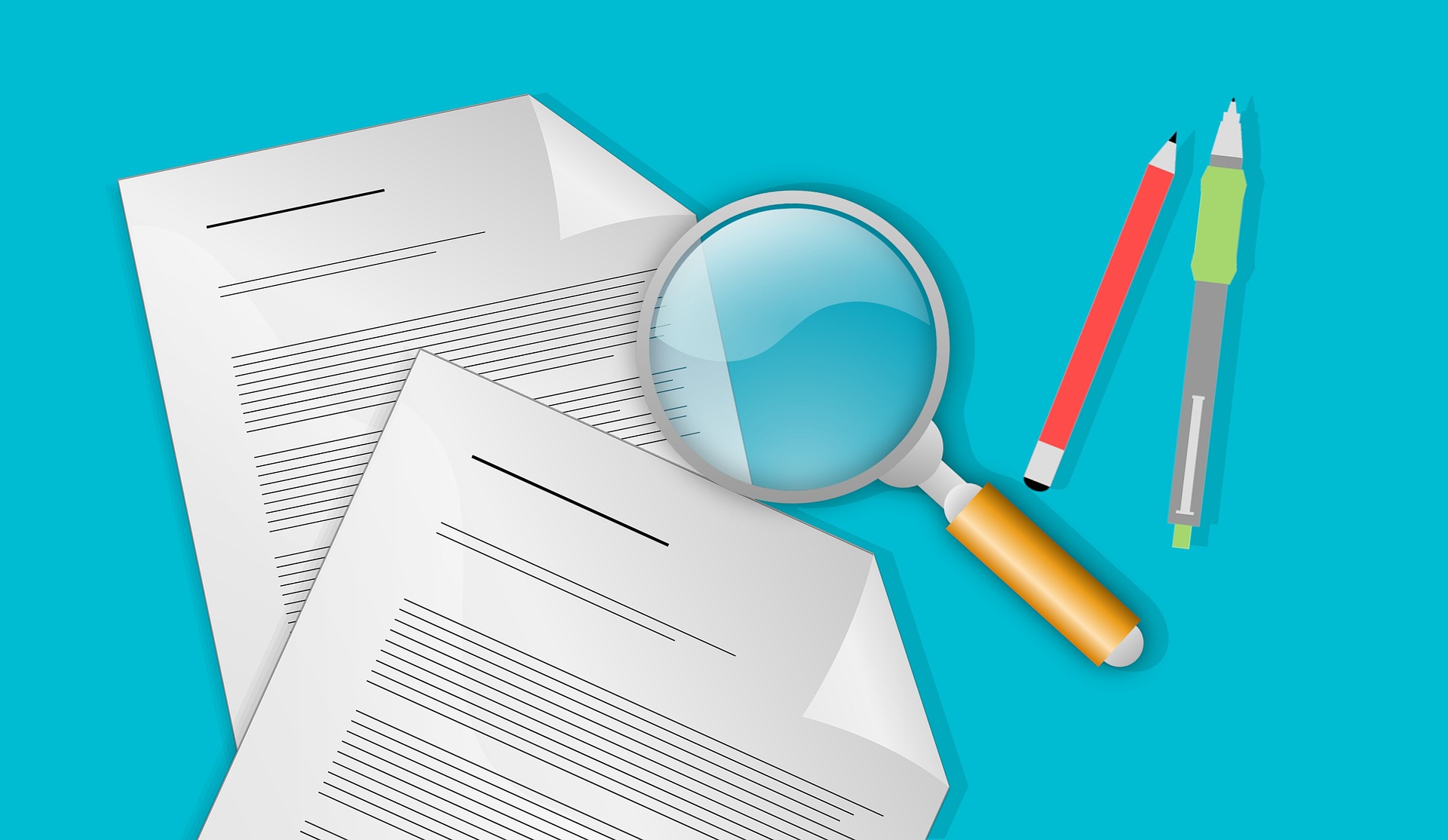

- 願書
- 特許請求の範囲
- 特許明細書
- 図面
- 要約書
願書
特許の願書とは、特許申請人が特許庁に対して特許権の取得を希望する旨を申し出る書類です。
特許の願書は、特許庁が定めた書式に従って正確に作成する必要があります。
特許の願書には、以下のような情報が記載されます。
・申請人の情報 申請人の名前、住所、国籍などが記載されます。
・申請日 特許申請の日付が記載されます。
特許請求の範囲
特許請求の範囲とは、特許出願者が特許の保護を求める範囲を定めた書類です。
発明品や製品の独自性を示すポイントとなります。
特許請求の範囲は、特許権の範囲を定めるために非常に重要な役割を担っています。
特許明細書
特許明細書とは、発明に関する技術的な詳細情報を記載する書類です。
特許明細書には、以下のような情報が記載されます。
・発明がどのような技術的背景をもっているのか記載されます。つまり、既存の技術に対する発明品の改良点や新しい技術的アプローチが説明されます。
・発明品の作り方や使用方法が記載されます。
・必要に応じて、後述する図面を引用しながら発明品の特徴を記載します。
図面
特許の図面は、発明品の外観や構造を図示したものです。
必ずしも必須ではありませんが、構造物の特許では、必須といえる書類です。
図面によって、発明品や製品の構造や機能がより具体的に説明されます。
要約書
要約書は発明の特徴を200字程度でまとめた書類です。
⑥各書類の様式・テンプレート
「知的財産相談・支援ポータルサイトの各種申請書類一覧(紙手続の様式)」をご参考ください。

以上が、特許申請に必要な書類の種類と役割になります。
申請に際しては、書類の提出期限や注意点なども確認しておくことが重要です。
いかに続いて解説していきます。
申請に際しては、書類の提出期限や注意点なども確認しておくことが重要です。
いかに続いて解説していきます。
特許申請書の作成方法とポイント
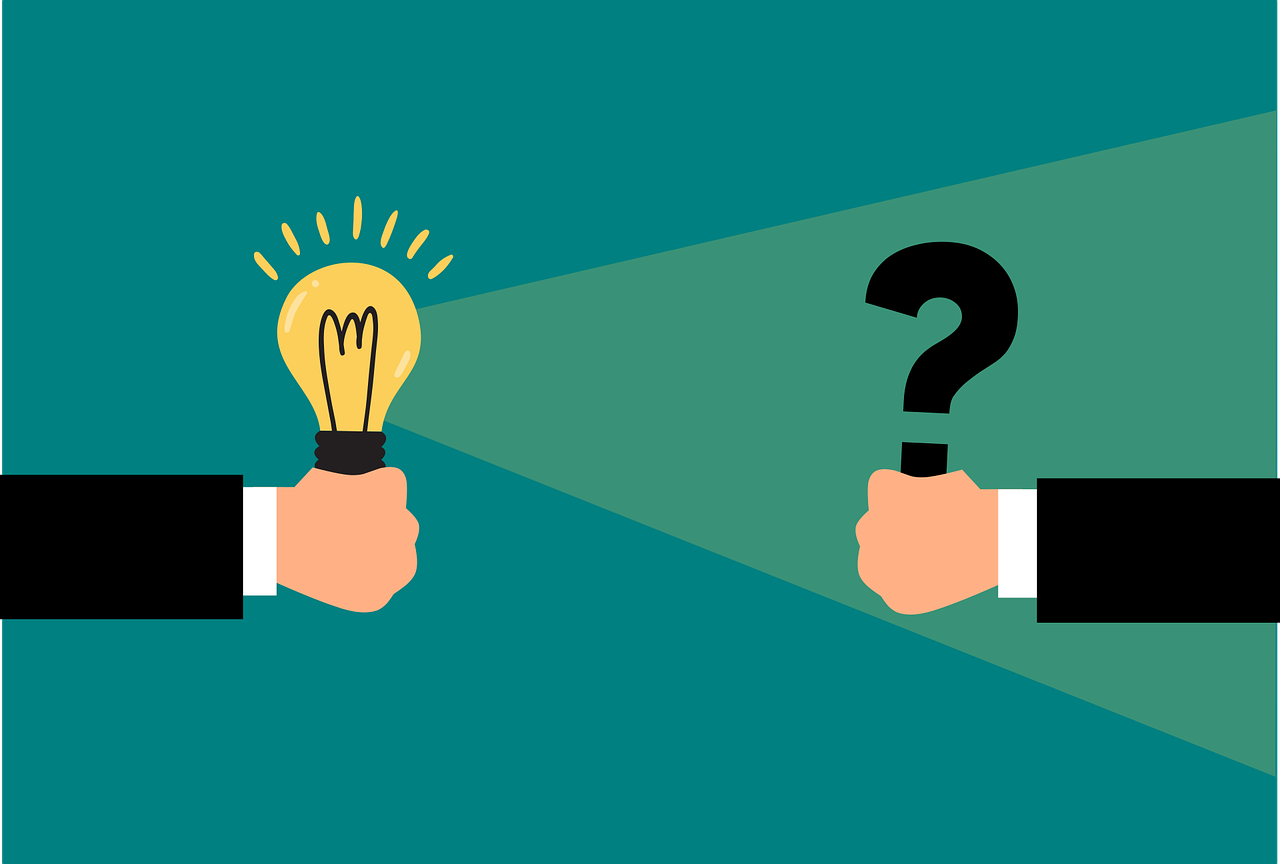

続いて特許明細書の書き方やポイントについて詳しく説明します。
特許請求の範囲の作成のポイント
特許請求の範囲では、発明の範囲を明確に定義する必要があります。
また、従来技術との違いを明確にするために必要なものです。
ただし、細かく書きすぎると、権利範囲が狭くなりますので、従来技術との違いがわかるポイントが明確になるように配慮することが必要です。
特許明細書の作成のポイント
特許明細書には、文章の明確化が重要です。
なるべく、文章は明確で簡潔な表現にしましょう。
特許審査官に発明のポイントがわかるように記載するのがポイントです。
また、必要に応じて、発明の実施例を記載することが望ましいです。
特に化学分野では実施例は必須といえます。
実施例は、発明の理解を深めるために重要な部分です。
図面の作成のポイント
図面は、特許明細書において、発明品の構造・形状・機能などを図示するための書類です。
以下に、図面の作成方法のポイントをまとめます。
・正確に詳細に描写すること
・図面には符号(番号)を記載すること 発明のそれぞれの構成要素に符号をつけて特許明細書で説明します。
・原則白黒であること 特許庁に申請する図面は原則白黒です。このため白黒でも明確になるように図面を描写する必要があります。
申請人・発明者の設定のポイント
特許申請においては、願書に申請人(出願人)と発明者を記載します。
申請人(出願人)は、特許権を取得する権利を有する人や団体です。
発明者は、発明を創造した人です。
特許申請のその他の注意点
特許申請・特許出願をすると、申請から1年半後に申請内容がインターネット上に公開されます。
ノウハウにして守りたい内容は申請書類に書かないように注意しましょう。
特に特許請求の範囲や特許明細書の記載は難しいことが多く、通常弁理士に依頼することが多いです。
もし困ったことがありましたら特許事務所BrandAgentがサポートしますのでお気軽にご相談ください。
特許申請の手続きの流れ


1.調査・分析
2.申請書類の作成
3.特許庁への申請
4.審査請求
5.審査結果の通知
6.登録料の納付、特許権の維持
1.調査・分析
発明品がすでに公知のものか調査・分析を行います。
この段階では、既存の特許文献をもとに調査されることが多いです。
2.申請書類の作成
特許申請書類を作成します。
特許申請書類には、上述の願書・特許請求の範囲・特許明細書・図面・要約書が含まれます。
特許申請書は、特許庁が定めた書式に従って作成する必要があります。
3.特許庁への申請
特許申請書類を特許庁に提出します。
ここでは申請手数料も併せて支払います。
特許出願書類の提出方法は以下の3つのいずれかです。
- 特許庁へ持ち込み
- 郵送
- オンライン
郵送の場合は以下の宛先へ郵送します。
郵送先
〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官
オンラインで出願することもできます。
ただし、電子証明書やICカードリーダーなどの準備が必要となり面倒です。
特許出願書類を提出するとき、出願手数料の納付も行います。
持ち込みまたは郵送の場合は、出願書類の1ページ目に14,000円分の特許印紙を貼り付けて支払います。
特許印紙の購入は、特許庁か全国の郵便局で可能です。
また持ち込み・郵送での申請では、別途書類の電子化手数料がかかるので注意が必要です。
出願書類を提出してから10日程度で電子化手数料の振込用紙が届きますので、それを使って振り込みます。
オンラインで申請した場合は、
出願手数料14,000円を以下のいずれかの方法で納付します。
- 電子現金納付(ペイジー)
- 口座振替
- 特許印紙の郵送
- 日本銀行窓口での現金納付(専用の納付書を使用)
提出後、特許庁は出願書を審査し、適切な審査結果を出します。
4.審査請求
実は特許出願(申請)だけでは、特許庁による審査は始まりませんので注意してください。
特許出願の日から、原則、3年以内の間に「出願審査請求」もする必要があります。
商標出願の場合は、「出願審査請求」は不要ですが、特許出願の場合は、「出願審査請求」が必要です。
この点は注意してください。
ここで、出願審査請求では、出願審査請求書と言われる書類と手数料の納付が必要になります。
出願審査請求をしないと、特許出願は却下されますのでこの点注意ください。
出願審査請求書を提出する
出願審査請求書の様式は、「知的財産相談・支援ポータルサイトの各種申請書類一覧(紙手続の様式)」から入手することができます。
(3.中間書類の様式の(5)その他より。)
出願審査請求書の書類の提出方法は以下の3つのいずれかであり、手数料の納付方法についても特許出願の提出と同様です。
- 特許庁へ持ち込み
- 郵送
- オンライン
ただし、出願審査の場合は、手数料が異なります。
5.審査結果の通知
審査が終わると、特許庁から審査結果が通知されます。
審査結果は以下の2とおりです。
- 審査が通った場合、登録査定が通知されます。
- 審査が通らなかった場合、拒絶理由が通知されます。
ここで、登録査定が通知された場合、通知の日(発送日)から30日以内に登録料を納める必要があります。
登録料を納めると、設定登録されて、特許をとることができます。
一方で、拒絶理由が通知される場合は、出願書類の修正(補正)・意見書の提出により、再審査をしてもらいます。
一発で審査に通る確率はとても低いです。
拒絶理由が通知されることは当たり前のように思っていた方がよいでしょう。
たいていの場合は1~2回の拒絶理由が通知されて、補正書と意見書を提出することにより登録されることが多いです。
6.登録料の納付、特許権の維持
特許権を取得した後は、特許権の維持に向けて、更新料の支払いや特許出願の内容の改善などを行う必要があります。
なお、特許庁におさめる費用についてはこちらの記事で解説していますのであわせてご参考ください。
-
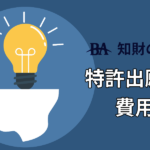
-
特許申請の費用を弁理士が解説
続きを見る
以上が、特許申請の手続きの流れについての基本的な説明です。
特許申請は、特に専門知識が必要であり、特許申請に関する規則や手続きに精通した専門家に相談することをおすすめします。
もし困ったことがありましたら特許事務所BrandAgentがサポートしますのでお気軽にご相談ください。
特許申請から登録までの費用はどれくらい?

特許出願から登録までの間に、特許庁に手数料・特許料を支払う必要があります。
また、弁理士に依頼する場合、弁理士報酬も支払う必要があります。
特許庁に支払う内訳は以下のとおり。
- 特許出願時 ¥14,000
- 出願審査請求時 ¥158,000(請求項の数を5とした場合。)
- 登録時 ¥9,300(請求項の数を5とした場合。3年分の納付料金)
特許庁に支払う費用のシステムは複雑であり、一律いくらというものではなく、出願書類の内容によって変わります。
そこで、ここでは平均的な料金(請求項の数が5であることを想定。)としています。
おおよそ¥200,000ほどかかることを想定しておけばよいでしょう。
さらに詳しい費用の解説はこちらで解説していますのでご参考ください。
-
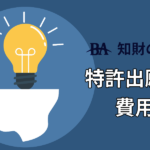
-
特許申請の費用を弁理士が解説
続きを見る
特許審査の流れと期間


- 1.審査請求の提出
- 2.審査官による審査
- 3.審査結果の通知
- 4.拒絶理由が通知された場合、申請人は補正書と意見書を提出します。
特許審査には、申請書の提出から特許登録までに数年以上の時間がかかる場合があります。
-
- 特許審査の期間は、審査請求のタイミングや、
特許庁の状況によって異なりますが、通常は申請してから2~4年程度とされています。
もし期間を早めたいのであれば審査請求を早めに済ませるだけでなく、早期審査の請求をすることをおすすめします。
早期審査を請求すれば通常申請から3か月~半年ほどで審査結果が通知されます。
参考:「特許出願の早期審査・早期審理について」
以上が、特許審査の流れと期間についての基本的な説明です。
特許審査には、専門的な知識が必要であるため、特許事務所や弁理士に相談することをおすすめします。
特許登録後の手続きと期間


1.特許査定の通知
2.登録料の支払い
3.特許証の交付
4.特許権の維持
1.特許査定の通知
特許審査が終了し、特許権が認められた場合には、特許登録の通知が届きます。
2.登録料の支払い
特許登録を行うためには、特許登録料を支払う必要があります。
支払い期限を過ぎると、特許登録が取り消される場合があります。
支払い期限は登録査定の発送日から30日以内です。
3.特許証の交付
特許登録料の支払いが完了すると、特許証が交付されます。
特許証には、特許番号や、申請日などが含まれます。
4.特許権の維持
特許権を維持するためには、年度ごとに年金を支払う必要があります。
特許権の有効期間は、特許法によって定められており、一般的に申請してから20年間です。
なお、登録料の費用についてはこちらの記事で解説しています。
-
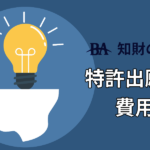
-
特許申請の費用を弁理士が解説
続きを見る
特許申請に関する注意点とポイント


1.特許調査・分析を実施すること
2.特許明細書には従来技術と発明との差別化が明確であるようにすること
3.申請人と発明者の情報は正確に記載すること
4.審査請求のタイミングをしっかりと確認すること
特許申請の前に、しっかりと既存の特許文献の調査・分析を行いましょう。
これにより、従来技術と発明との差異が明確になり、特許明細書にもその際が明確に記載しやすくなります。
結果として、特許をとりやすくなります。
また、申請人・発明者の情報は原則あとから変更できないのでしっかりと確認して正確に記載しましょう。
審査請求は必須ですので忘れずに請求をしておきましょう。
以上が、特許申請に関する注意点とポイントについての基本的な説明です。
特許申請には、専門的な知識や経験が必要であるため、特許事務所や弁理士に相談することをおすすめします。
特許申請においては、上記のポイントを押さえた正確かつ効果的な手続きが重要です。
もし困ったことがありましたら特許事務所BrandAgentがサポートしますのでお気軽にご相談ください。
特許の取り方のコツ

特許申請をしたものの、登録できないケースは多いです。
そこで、ここでは特許申請で失敗しないための重要なポイントを解説していきます。
重要なポイントは以下のとおり。
- 特許の申請はできるだけ早く
- 特許の申請をするまでは内容は公開しない
順番に解説します。
特許の申請はできるだけ早く
特許権は早いもの勝ちです。
似たような内容の発明が先に登録されていた場合、特許をとることができませんので、できる限り早く出願をすませておくことが重要です。
また似たような内容の発明が登録されていなくても、日本国内外でその内容が知れ渡ってしまうと、公知の発明とみなされて特許をとることができないため注意してください。
特許の申請をするまでは内容は公開しない
さきほど、解説したように、日本国内外で発明の内容が知れ渡ってしまうと、公知の発明とみなされて特許がとれません。
このため、出願をするまでは発明の内容を公開しないようにしておくことが重要です。
例えば、技術発表などで公の場で発明の内容を公開してしまうと、原則、特許をとることはできなくなります。(この場合、救済措置がありますがこれについてはまた別途お話しします。)
そのため出願はなるべく早く済ませ、出願をするまでは内容を公開しないことが特許出願で失敗しないために重要です。
特許申請を個人でやるか弁理士に代行するか
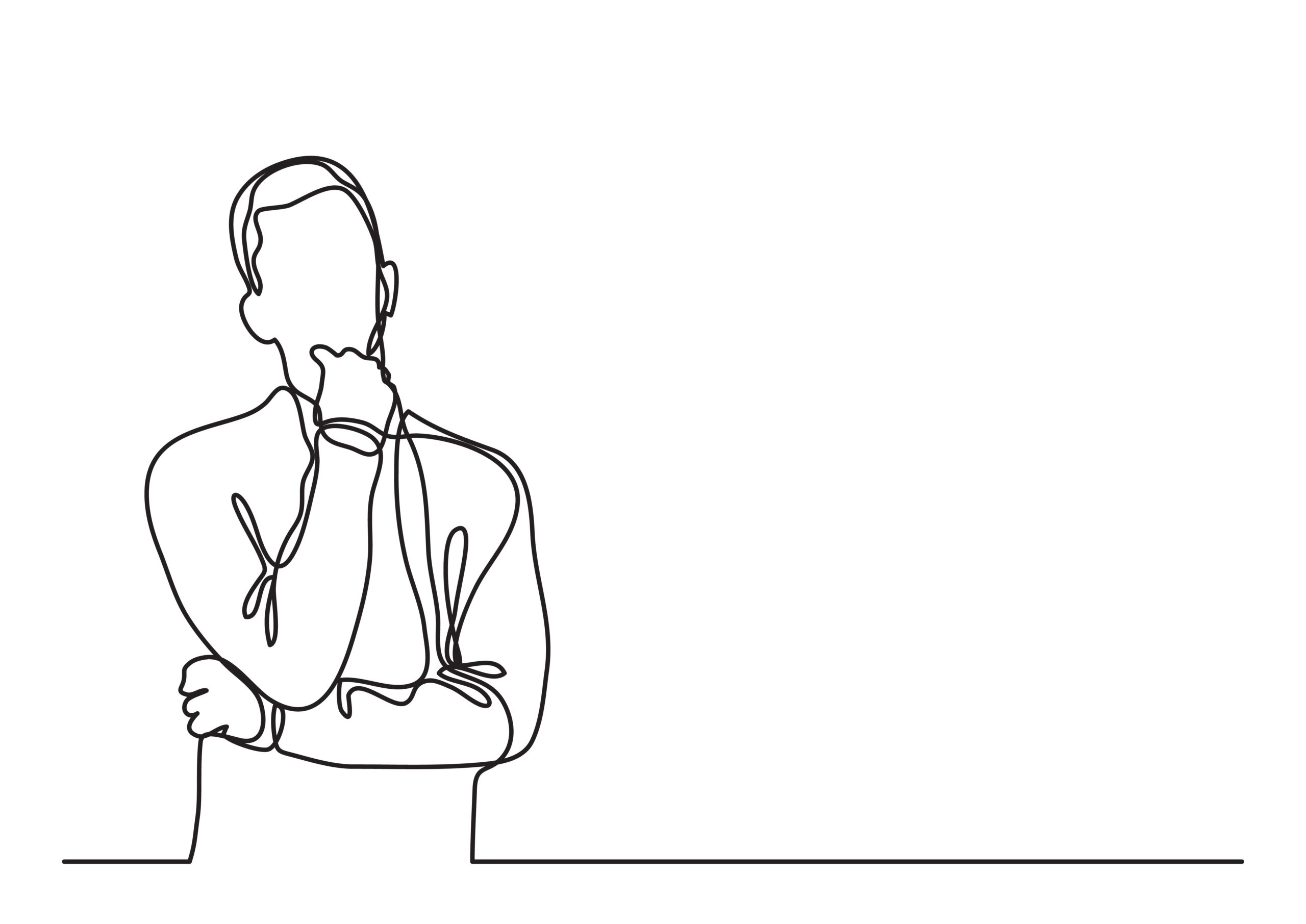
弁理士に特許出願を依頼すると、費用が大きくなるというデメリットがあります。
その一方で、弁理士に依頼すると、以下のメリットがあります。
- 特許の登録可能性が高くなる。
- あなたが特許権で取りたい権利範囲をとりやすくなる。
弁理士は特許のプロです。
確かに弁理士報酬により費用は大きくなりますが、ほしい権利範囲で、より確実に特許をとりたいのであれば、弁理士に依頼することをおすすめします。
特許申請のまとめ

以上、特許の取り方と特許申請の方法をまとめました。
このブログでは、今後も特許の基礎知識について解説していきますのでご参考いただけますと幸いです。
特許事務所BrandAgentではこれまで1,000件以上特許をサポートした弁理士が対応しますのでぜひご利用いただければと思います。
